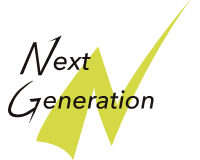座談会「ネクジェネいまむかし」(第2弾)
ネクジェネには、現在活動しているメンバーだけでなく、これまで多くの若者たちが関わり、卒業後もそれぞれの場所で活躍しています。創立9周年を迎える2025年、これまでの歩みを振り返り、組織の変遷や当時の雰囲気を伝えていくことを目的に、過去のスタッフとの座談会企画「ネクジェネいまむかし」をスタートしました。
第2回となる今回は、団体が一気に生産性を高め、長期事業に踏み込んでいった拡大期(2019〜2022年)を振り返ります。ゲストは、当時 Eva Lab を中心に学習支援と政策部を引っ張った川端舞穂さん(社会人4年目)と、前橋市高校生学習室で室長も務めた高橋海成さん(社会人2年目)です。
まだ組織のノウハウも十分とは言えなかったこの時期をどのように乗り越えてきたのか。そして、その経験が今どんな形で生きているのか。お二人の記憶をたどります。
今回の参加者
- ゲスト:小高 広大(こだか こうだい)
NPO法人Next Generation 理事長 - ゲスト:川端 舞穂(かわばた まいほ)
自治体職員
元 特定非営利活動法人 Next Generation 副理事長 - ゲスト:高橋 海成(たかはし かいせい)
国内大手旅行会社
元 特定非営利活動法人 Next Generation 副理事長
元 前橋市高校生学習室 室長(2022年度) - ファシリテーター:菊川 心平(きくかわ しんぺい)
立命館アジア太平洋大学 3年
NPO法人Next Generation 理事
“拡大期”ってどんな時代だった?
《菊川》
本日はお忙しい中ありがとうございます。
まずは今回の企画について、簡単にご説明させていただきます。
ちょうど今、活動報告書として使っているネクジェネの沿革資料が手元にあるんですが(法人概要資料を画面共有しながら)、このあたりですね。2019年9月に前橋中央通り商店街にフリースペース「Eva Lab」を立ち上げて、前橋市高校生学習室の開室を挟みながら、そのままコロナ禍に突入していく時代。
今はこの時代を、ネクジェネの「拡大期」として定義しています。今回は、その時期に活躍されていたお二人にお越しいただき、当時どんなことをしていたのか、そしてどんな学びが今に活かされているのかを伺えればと思います。
《小高》
僕からも少し補足すると、海成が高校3年の時に Eva Lab で受験勉強をしていて、舞穂はちょうど大学2年生くらいだったよね。
《川端》
そうですね。メインで関わっていたのは大学2年生から社会人1年目頃までだったと思います。
《小高》
あの時、年が明けてすぐに前橋市長選挙があって、みんなで見に行ったり。途中で海成が急にフェードアウトしたと思ったら、半年後に戻ってきて、学習室の室長をやったり……。
《高橋》
消えてないですよ!(笑)
旅行業の国家資格を取りに行ったり、いろいろしてたんです。
《小高》
まあ、とにかくいろいろやってたよね。「Eva部」とか覚えてる?
「職業図鑑を作るんだ!」って言っていた頃の時期。
だから今回は、ちょうど菊川が知らないことも多い時期だと思うので、どんどん聞いていってもらって、二人から当時の様子を引き出してもらえればと思います。
ビラ配りと“痛い失敗”から学んだこと
《小高》
当時の記憶ってどう?
《川端》
2022年の記憶は、あまり残ってないかもしれないです。多分、社会人1年目で、そこまで深く関われていなかったからかな。
一番記憶に残っているのは、ベネッセの補助金を獲得して学習支援を立ち上げた頃(2020年下半期)と……あとは「ビラ配り」ですね(笑)。
《小高》
あ〜、ビラ配りね。
《川端》
前橋市内の市営団地を調べて、みんなで車に乗って、怪しい集団みたいになりながら、ひたすら全ての団地にポスティングしていくっていう。
今思うと、すごくアホみたいなことをしてたなって(笑)。
でも当時は、「この事業は絶対にいいものだし、必要としている人が必ずいる」という確信があったんですよね。
《小高》
めちゃくちゃ自信がある事業だったからね。
《川端》
そう。だから「宣伝さえすれば絶対来てくれる」と思って、ひたすらポスティングをしたんですけど……蓋を開けてみたら…。
《小高》
一人だけ来たんだよね。何千枚配ったっけ?多分3000枚とかかな。市内の市営団地を回ってポスティングしてきたんだよね。
あれが2020年、コロナ禍の秋だったかな。
《川端》
そうそう。でも「これは絶対、結果に繋がる」と信じてた。
でも結局、「どんなにいいものでも、伝え方が一番大事なんだな」と痛感した経験になりました。今思えば、あのポスティングの仕方は怪しすぎて怖いし、大切なお子さまを、見ず知らずの団体に預けようとは思わないですよね。
その感覚は今でも大事にしていますし、あの経験があってよかったなと思っています。
《小高》
やっぱり当時は若かったな、と思うところもあるし、そもそもネクジェネ自体の知名度が、当時はあまりなかったよね。
今なら技術も進んで、市内の小学校向けに一瞬でタブレット配信できるようになったけど、あの頃は「信頼」という面でまだまだ足りなかった時代なのかな。
《川端》
そこまで考える頭も、当時の私たちにはなかった時期だったよね。
《小高》
逆に今は、そのときの失敗も全部、僕の中で「歴史」として蓄積されているから、その分だけ楽な面もあるよね。
ポスティングなんて、今もし話題に上がってきたら「あ〜、それは無理無理」ってすぐ言える(笑)。
《川端》
私たちが痛い目を見た経験が、いまの“先人の知恵”になっている感じだよね。「同じ失敗はするなよ」っていう(笑)。
月イチイベントと“サードプレイス”への手応え
《小高》
海成はどう?
《高橋》
室長をやっていたときの記憶としては、「月1で何かしらイベントをやっていたな」という印象が強いです。
寿吏央さんがファッションの企画をやったり、亀ちゃんがダイエット講座をやったり。2019〜2021年くらいは、舞穂さんや小高さんなど、関わる人がある程度限られていたと思うんですけど、2022年ごろからはいろんな人を巻き込めるようになっていった気がします。
イベントの良し悪しは置いておいて、自分にとってはすごく貴重な経験でした。
《小高》
どんなところが、自分の中で役に立っていると思う?
《高橋》
それまでは、本来は人に任せた方がよいことでも、「自分でやったほうが早い」と思って抱え込んでしまうことが多かったんです。でも、あえて人に頼ることで、いろんな人の新たな一面が見えてきて、すごく良かったなと思っています。
その中でも一番印象に残っているのが、2022年8月に実施した進路イベントです。
すごく大変でしたけど、「学習室を居場所として考えてくれている人がこんなにいるんだ」と実感できました。想像以上に学習室の卒業生が来てくれて、10人以上の卒業生が参加してくれたんじゃないかな。
《小高》
(当時の Instagram 投稿を共有しながら)これだよね。
《高橋》
そうです、それです。
最初に掲げていたコンセプトが「アクエルを高校生のサードプレイスに」というものでしたが、その目標がひとつの形になったイベントだったのかなと思います。
《小高》
学習室が始まって1年目の進路イベントだったからね。かなり多くの人に来てもらえたよね。
《高橋》
ああでもない、こうでもないと言いながら準備して、最終的には50人くらい来てくれて。「やってよかったな」と心から思えたイベントでした。
「アクティブプレイス」とコロナ禍の動き方
《小高》
イベントの話で言うと、2019〜2022年はいろいろなことを同時並行でやってたよね。
(2022年の事業計画書を見ながら)みんな、「アクティブプレイス」って覚えてる?
《川端》
あ〜、思い出した!
《高橋》
なんでしたっけ、あれ……。
《小高》
あれは、下仁田でやっていた二年目の事業だね。2021・2022年と下仁田で活動していて、初年度が「下仁田土曜スクール」、二年目が「アクティブプレイス」だった。
今だったら、あんな名前はつけないよね(笑)。
この年は、スマホ講座もたくさんやってたよね。
《高橋》
え、今はもうやってないんですか?
《小高》
今はやってないね。移動も多くて、なかなか大変だから。
《高橋》
でも、あれ、今の仕事でめちゃくちゃ役立ってますよ。
《小高》
お、そこ詳しく聞きたいな。
スマホ講座と「伝えること」の原点
《高橋》
僕の仕事は、性別や年齢に関係なく、不特定多数のお客様に対応する仕事なんですけど、スマホ講座って「いかに分かりやすく伝えるか」が本当に重要で。
その“伝え方”を考える経験が、すごく学びになったと思います。
《小高》
意外と「人に伝えること」の原点みたいな感じがするよね。
僕たちはスマホの使い方は分かっているけれど、その知識をどう噛み砕いて伝えるかが腕の見せ所というか。
《高橋》
そうなんですよ。自分たちなら何も考えずにできるところでも、人に教えるとなると全部言語化しなきゃいけない。
最初は、その“足並みをそろえて教える”部分がめちゃくちゃ大変でした。
《小高》
菊川もスマホ講座をやって、大失敗したことあったよね。
《菊川》
あ〜、あれですね。見よう見まねでやったら、完全に学級崩壊しました(笑)。
《小高》
菊川は難しいことをいっぱい知ってるんだけど、伝えるときに取捨選択ができないというか。
全部伝えようとするから、おじいちゃん・おばあちゃんたちは訳がわからなくなって、最後にはみんな好き勝手なことを始めちゃってね。
だからある意味、ネクジェネスタッフにとって「伝えることの原点」はスマホ講座にあったのかもしれないね。
「政策部」という実験:組織化への一歩
《小高》
ここまでいろいろ話してきたけど、菊川から何か深掘りしたいことある?
《菊川》
そうですね……。舞穂さんの時代の話を聞いていると、「みんなで話し合いながら物事を進めていた」印象があって。
今は小高さんが主導して進めてくださっていますが、その辺りの“意思決定の仕方”って、当時どうなっていたんですか?
《小高》
あ〜、いいところついてきたね。当時の意思決定の話をしようか。
《川端》
今のスタッフって、小高さんとの年齢差もあって、“先生”とか“かなり上の先輩”みたいに思っている子も多いかもしれないよね。
どうしても、小高さんが答えを持っているから、「教える/教えてもらう」の上下関係ができやすい。みんなもそれを頼れば効率よく動けるから、あまり試行錯誤の過程を踏まずに進んでしまっているように感じることもあります。
でも当時は、もっと対等な感じで、意見がぶつかることも多かったし、決して今みたいな感じではなかったよね。
《菊川》
そうだったんですね。
《川端》
うん。みんなが自分の頭で考えて捻り出すプロセスがあったからこそ、さっきの“ポスティング事件”みたいなことも起きた(笑)。
無意味なこともたくさんやったと思うけど、でもそれが今に繋がっているんだろうなって思います。
《小高》
当時は、「政策部」っていう部署をつくっていてね。
事業開発部に近いイメージで、方針を決めて、それを現場に振っていく役割を担っていました。それまでみんなでダラダラ話して決めていたところに、各部署から“頭の回転が早い人たち”を集めて、組織として引っ張ってもらうイメージだった。
《川端》
それまで横並びでやってきたところに、急に上下関係ができてしまった感じもあって。よく思わない人もいましたし、組織としてバチバチしてた時期だったなと思います。
でもネクジェネが大きくなっていくためには、必要なステップだったのかなとも感じています。
《小高》
仕組み自体は行政がモデルになっていて、行政って、政策部門が方針を作って現場に説明して回していくじゃない?
「そのほうが効率的なんじゃないか」と思って始めたのが政策部でした。
《川端》
ネクジェネって、社会人経験の前段階のメンバーが多いから、そういう“上から方針が降りてくる”構図を、どうしても理不尽に感じてしまうこともあったと思います。
でも社会に出てみると、「あれはあれで当たり前のやり方だったな」と思う部分もありますね。
今の生活・仕事にどう活きている?
《菊川》
ここまでのお話を聞いて、本当にいろいろな経験をされてきたんだなと感じました。
最後に、ネクジェネでの経験が今の生活や仕事にどう活きているのか、教えていただけますか?
《川端》
やっぱり、いろんなことを自由にやらせてもらえたからこそ、とりあえずチャレンジしてみて、修正していくという習慣が身についたと思います。
手探りでやっていた分、「いいと思ったらまずやってみる。ダメなら改善してもう一回チャレンジする」というやり方が自然と身につきました。とても貴重な環境でしたね。
あとは、仕事をするときにある程度の見通しを立てることができるようになったと思います。もともと自分にすごく自信があったタイプではないんですが、急に仕事を振られても対応できる力はネクジェネで鍛えられました。
今も、一見難しそうな案件が来ても、そこまで怯まずに向き合えるのは、大学時代にネクジェネを経験していたからだと思います。
《菊川》
高橋さんはいかがですか?
《高橋》
今もネクジェネにいた当時も、「形のないものをお客様に届ける」仕事をしている感覚があって。
その時に必要になる“説得力”とか、“行政との関わり方”、“プロポーザルの書き方”、“後輩の育成”といった、仕事の基礎となる部分は、ほとんどネクジェネで学んだなと感じています。
さっき舞穂さんも言っていたように、「やりたいことをやらせてくれる環境」だったからこそ、自分の強み・弱みも含めて全部知ることができた2年間でした。
ネクジェネにいなかったら出会えなかった人たちもたくさんいるし、コロナ禍の大学生活で、もしかしたら何もせずに過ごしていたかもしれないことを思うと、本当に感謝しています。
もしネクジェネに出会っていなかったら?
《菊川》
小高さん、お二人の話を聞いていかがですか?
《小高》
逆に、二人にもう一個だけ質問させて。
もしネクジェネに出会っていなかったら、今と同じ場所で働いて、同じ生活をしていたと思う?
《川端》
じゃあ私から。
多分、保健師を目指していたのは元々だったので、「保健師になる」ところまでは同じだったかもしれない。でも、社会人4年目まで今のように続けられていたかと言われると、かなり怪しいなと思います。
仕事をする上での「人との関係性の築き方」とか、「困難にぶつかったときにどう乗り越えるか」という部分は、ネクジェネで一番鍛えられたところでした。
就職してからも大変なことはたくさんありましたが、ネクジェネのことを思い出しながら乗り越えてこられたので、大学時代に鍛えられていなかったら今の自分はいなかっただろうなと思います。
《高橋》
僕も、旅行会社に入りたいという気持ちはきっと変わっていなかったと思います。でも、社会人2年目で今ほど成長できていたかといえば、全然違っただろうなと。
もしかしたら、ネクジェネに入っていなかったら群馬で就職していたかもしれないし、全国区の会社に挑戦するという発想もなかったかもしれません。
ネクジェネで活動して「外の世界」を見られたからこそ、今の選択に繋がったんだと思います。
正直に言えば、この活動を就職活動で話したら、面接でかなり刺さった実感もあります(笑)。
ネクジェネでの仕事は、これまで24年生きてきた中で一番しんどかったです。パソコンもまともに使えないところから、資料のまとめ方も分からないまま締切に追われて事業を進めて、それでも自分についてきてくれる人たちがいる。
今、仕事で辛いことがあっても「ネクジェネのときよりは早く帰れるしな」「今は答えを持っている人が周りにいるしな」と思える。いろんな場面で、あの2年間が支えになっています。
先輩たちの背中から、今のスタッフへ
《菊川》
お二人のお話を聞いて、ネクジェネでの時間が、その後のキャリアや生き方にとって大きな推進力になっていることが伝わってきました。
《小高》
前回の座談会で、萌那は「育ててもらった」という表現をしていたけれど、今日の二人の話を聞いていると、「自分で勝手に育っていってくれた」という表現のほうが近いのかなと感じました。
それと同時に、今のネクジェネと過去のネクジェネを比べると、自分の中で少し“孤独感”のようなものを感じることもあります。
今は自分が中心にいて、その周りに現役スタッフがいる構図だけれど、昔はもっと横並びで一緒に進んでいた感覚が強かったな、と。
《菊川》
今日のお話を聞いて、僕ら現役世代ももっと頑張らなきゃなと思いました。
お二人とも、本日はお忙しい中ありがとうございました。続きはまた、地元に戻ってきたときに、ぜひゆっくりお話しさせてください。